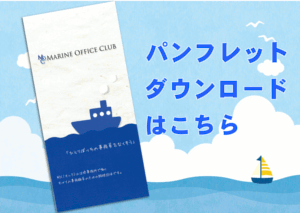執行官の事務に関する記録及び帳簿の作成及び保管並びに現況調査の手数料の加算の基準について
最高裁民三第125号
(組い-2)
平成9年3月13日
改正 平成10年11月19日民三第575号
平成11年6月15日民三第266号
平成14年2月15日民三第42号
平成15年3月26日民三第143号
平成16年2月6日民三第46号
平成16年12月1日民三第000111号
平成17年12月12日民三第001005号
平成18年2月8日民三第000031号
平成20年11月18日民三第000906号
平成20年12月11日民三第000960号
平成26年3月20日民三第276号
令和2年1月21日民三第681号
令和2年9月4日民三第388号
令和3年6月28日民三第195号
令和3年11月26日民三第303号
令和4年7月28日民三第257号
令和5年2月10日民三第18号
令和5年6月27日民三第216号
地方裁判所長 殿
最高裁判所事務総長 泉 徳 治
執行官の事務に関する記録及び帳簿の作成及び保管並びに現況調査の手数料の加算の基準について(依命通達)
執行官規則(昭和41年最高裁判所規則第10号)第20条の規定による執行官の事務に関する記録及び帳簿の作成及び保管並びに執行官の手数料及び費用に関する規則(同年最高裁判所規則第15号)第18条第2項の規定による現況調査の手数料の加算の基準について下記のとおり定めましたので、これによってください。
記
第1 記録の作成及び保管
1 記録符号
執行官の取り扱う事件のうち、別表第1の「事件種別」欄に掲げる事務を内容とする事件については、同表「記録符号」欄に掲げる記録符号を付する。
2 記録の作成等
(1) 記録符号が定められている事件については、1件ごとに記録を作成する。
(2) 記録符号が定められていない事件については、事件の種別ごとに、申立書その他の書類を受付又は作成の順序に従ってつづり込み、司法年度ごとに取りまとめる(司法年度ごとに取りまとめたものを「簿冊」という。以下同じ。)。ただし、必要と認める場合には、1件ごとの記録を作成することができる。
(3) 記録には、別紙様式第1による表紙を付し、当該事件に関する申立書、調書その他の書類を受付又は作成の順序に従ってつづり込む。
(4) 閲覧等の制限の申立て及び秘匿の申立てに係る書類の取扱い
ア 次の書類については、(ア)と(イ)及び(ウ)とに分けてそれぞれ別冊とし、(2)及び(3)の定めにかかわらず、関係する書類ごとに編年体によりつづり込む。
(ア) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第92条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による秘密記載部分の閲覧等の制限の申立てがされた書類
(イ) 別表第1の「事件種別」欄に掲げる事務を内容とする事件のうち、当事者の申立てによるものについて、秘匿事項届出書面(民事訴訟法第133条第2項(他の法律において準用する場合を含む。))及び同法第133条の2第2項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による秘匿事項記載部分の閲覧等の制限の申立てがされた書類
(ウ) 別表第1の「事件種別」欄に掲げる事務を内容とする事件のうち、当事者の申立てによるものについて、民事訴訟法第133条の4第2項(他の法律において準用する場合を含む。)の許可の裁判の確定に伴い、民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号)第52条の11第6項(他の規則において準用する場合を含む。)の規定により提出される許可の対象でない部分を除いた書類及び同規則第52条の13第1項(他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される閲覧等用秘匿事項届出書面
イ アの定めにより別冊とした書類のうち、秘匿の申立て若しくは閲覧等の制限の申立てが取り下げられ、又はこれらの申立ての却下決定若しくは秘匿決定の取消決定若しくは閲覧等制限決定の取消決定が確定して、閲覧等の制限がされる部分がなくなったものは、(2)及び(3)の定めに従ってつづり込む。
ウ 民事訴訟規則第34条第3項本文、第5項本文又は第7項(これらの規定を他の規則において準用する場合を含む。)の規定により提出される秘密記載部分を除いた書類、同規則第52条の11第3項、第5項本文又は第6項(これらの規定を他の規則において準用する場合を含む。)の規定により提出される秘匿事項記載部分を除いた書類(アの(ウ)に該当するものを除く。)及び同規則第52条の13第1項の規定により提出される閲覧等用秘匿事項届出書面(アの(ウ)に該当するものを除く。)は、(2)及び(3)の定めに従ってつづり込む。
3 記録及び簿冊(いずれも別冊を含む。以下同じ。)の保管
(1) 保管者等
ア 記録は、当該事件を担当する執行官が保管する。
イ 簿冊は、執行官室に備え置く。
(2) 保管の方法
ア 保管の場所
(ア) 記録及び簿冊は、施錠のできる保管庫又は保管に適する倉庫に収納して保管する。
(イ) 保管庫は、執務時間中においても、看守する者がいない場合には、施錠をする。
イ 保管に当たっての整理
記録及び簿冊の保管に当たっては、記録の保管者ごとにこれを区分した上、事件の種類ごとに大別し、事件番号の順序又は事件の進行状況に応じた順序に従うなどして、整然と整理する。
なお、閲覧等の制限の申立てのあった事件記録(閲覧等制限決定のされたものを含む。)及び秘匿決定の申立てのあった事件記録(秘匿決定のされたものを含む。)は、表紙にその旨を明示するなどして、その取扱いに留意する。
4 記録及び簿冊の保存及び廃棄
(1) 保存の時期等
記録については当該事件の終局後、簿冊については当該司法年度の経過後、速やかに必要な整理をし、これを保存に付する。
(2) 保存期間及び特別保存
ア 記録及び簿冊の保存期間は、5年間とし、記録については当該事件の終局の日から、簿冊については当該司法年度の翌年度の初日から起算する。
イ 保存期間が満了した記録及び簿冊で、特別の事由により更に保存する必要があるものは、その事由のある間、これを特別保存に付する。
(3) 保存の方法
ア 保存に付する記録及び簿冊には、これらの表紙その他の見やすい箇所に保存の終期を記載する。
イ 特別保存に付する記録及び簿冊については、これらの表紙その他の見やすい箇所に「特別保存」と朱書する。
ウ ア又はイの手続を終えた記録及び簿冊は、倉庫又は保管庫に種類ごと、年度ごと等の一定の区分を設けて保存する。
(4) 廃棄の時期及び方法
ア 記録及び簿冊の廃棄は、毎年、前年度中に保存期間が満了したものについて、所属の地方裁判所の認可を受けて行う。
イ 記録及び簿冊の廃棄は、監督補佐官が立ち会った上、焼却又は細断の方法により行う。
ウ イにより細断したものは、物品管理官又は分任物品管理官に引き継ぐ。
第2 帳簿等の作成及び保管
1 帳簿等の備付け
執行官室には、別表第2の「帳簿等の名称」欄に掲げる帳簿及び物品保管票(以下「帳簿等」という。)を備え付ける。
2 帳簿等の様式
(1) 帳簿等の様式は、別紙様式第2から別紙様式第11までのとおりとする(別表第2参照)。
(2) 所属の地方裁判所の認可を受けた場合には、定められた記載事項を省略しない限り、帳簿等の様式を適宜変更し、又はこの通達に定めるもの以外の帳簿等を備え付けることができる。
3 帳簿等の使用方法
(1) 事件簿(別紙様式第2から別紙様式第6まで)
ア 別表第2の「帳簿等の名称」欄に掲げる各事件簿(以下「事件簿」という。)は、司法年度ごとに作成し、備え置く。ただし、所属の地方裁判所の定めるところにより、事件が係属した時に作成することができる。
イ 事件簿には、当該年度中に受け付けた別表第2の「登載する事件」欄に掲げる事件に関する事項を登載する。
なお、前年度以前の年度の未済事件を当該年度の事件簿の冒頭に移記することは差し支えなく、この場合には、未済事件が登載されていた事件簿の「事件簿備考(別紙様式第6にあっては「備考」)」にその旨を記載する。
ウ 強制執行等事件簿、不動産等売却事件簿及び現況調査等事件簿は、バインダーにとじ、登載された全事件について記載を終えた時又はイのなお書きの定めにより移記した時に、バインダーから取り外して製本する。ただし、当該年度を経過した時に製本することも、差し支えない。
エ 強制執行等事件簿は、記録符号が執イ、執ロ及び執ハの事件ごとに区分し、又は別冊とする。
オ 不動産等売却事件簿、現況調査等事件簿及び拒絶証書作成等事件簿は、事件の種類ごとに区分し、又は別冊とすることができる。
カ 民事送達等事件簿は、民事送達事件にあっては、裁判所の命令によるもの及び当事者の申立てによるものの別により、事件の種類ごとに区分し、又は別冊とすることができる。
(2) 閲覧及び謄本等交付簿(別紙様式第7)
ア 閲覧及び謄本等交付簿は、司法年度ごとに作成し、備え置く。
イ 閲覧及び謄本等交付簿には、記録の閲覧、その謄本及び抄本の交付並びに執行官が取り扱った事務に関する証明書の交付の請求に関する事項を登載する。
(3) 事件関係送付簿(別紙様式第8)
ア 事件関係送付簿は、司法年度ごとに作成し、備え置く。この場合において、事項ごとに区分し、又は別冊とすることができる。
イ 事件関係送付簿には、事件に関する書類を送付する場合であって、他の帳簿等を使用しないときに、当該書類に関する事項を登載する。
(4) 執行官収支明細簿(別紙様式第9)
ア 執行官収支明細簿は、司法年度ごとに作成し、備え置く。
イ 執行官収支明細簿には、手数料、書記料(民事執行法(昭和54年法律第4号。以下「法」という。)第161条第6項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用及び執行官の手数料及び費用に関する規則第39条第2号に規定する執行裁判所に差し出すべき届書の作成の費用を含む。)、旅費及び宿泊料の収入並びに執行官室における経費の支出に関する事項を登載する。
(5) 物品保管票(別紙様式第10)
物品保管票は、執行官が職務上保管すべき有価証券その他の物品について事件ごとに作成し、備え置く。
(6) 帳簿等保存簿(別紙様式第11)
ア 帳簿等保存簿は、司法年度ごとに作成し、備え置く。この場合において、帳簿等及び簿冊の種類ごとに区分し、又は別冊とすることができる。
イ 帳簿等保存簿には、保存すべき全ての帳簿等及び簿冊に関する事項を登載する。
(7) 帳簿のとじ合わせ
司法年度ごとに作成するものとされている帳簿については、数年度分をとじ合わせ、又は同じ年度の数種の帳簿をとじ合わせることができる。
4 帳簿等の保存及び廃棄
(1) 保存のための整理
ア 帳簿についてはその記載を終えた司法年度の経過後、物品保管票については当該事件が終局した司法年度の経過後、速やかに必要な整理をし、これを保存に付する。
イ 帳簿を保存に付する場合には、当該帳簿の取扱責任者が最後に記載した欄の次の欄に、記載を終えた旨及びその年月日を記載して認印する。
ウ 物品保管票を保存に付する場合には、当該保管票が既済となった司法年度ごとに、番号の順に取りまとめる。
(2) 保存期間及び特別保存
ア 帳簿等の保存期間は、別表第2の「保存期間」欄に掲げる期間とし、帳簿については、その記載を終えた司法年度の翌年度の初日から、物品保管票については、当該事件が終局した司法年度の翌年度の初日から起算する。
イ 保存期間が満了した帳簿等で、特別の事由により更に保存する必要があるものは、その事由のある間、これを特別保存に付する。
(3) 保存の方法
第1の4の(3)の例による。
(4) 廃棄の時期及び方法
第1の4の(4)の例による。
第3 現況調査の手数料の加算の基準
執行官の手数料及び費用に関する規則第18条第2項の規定による現況調査の手数料の加算の基準については、次に定めるところによる。
1 手数料の加算額は、次に掲げる金額の範囲内において相当と認める額とする。
(1) 2以上の不動産又は船舶について現況調査をした場合には、21,500円に当該不動産又は船舶の数から1を減じた数を乗じた額
(2) 1不動産又は1船舶につき2以上のア又はイに掲げる占有関係について調査をした場合には、15,000円に当該占有関係の数から各1を減じた数を乗じた額
ア 現況調査の目的物の占有者が所有者以外の者である場合のその者の占有関係
イ 現況調査の目的物が建物である場合において、その敷地の所有者が当該建物の所有者以外の者であるとき(当該敷地が現況調査の目的物である場合を除く。)の建物の所有者の敷地に対する占有関係
2 1に定める加算のほか、調査のために要した労力、時間等により、特に必要があると認める場合には、86,000円を超えない範囲内において手数料を加算することができる。
付 記
1 実施
この通達は、平成9年4月1日から実施する。
2 通達の廃止
昭和55年8月28日付け最高裁民三第892号事務総長依命通達「執行官の事務に関する記録の作成及び保管等について」は、平成9年3月31日限り、廃止する。
3 経過措置
(1) この通達の実施前に申し立てられた民事執行の事件に係る記録符号については、なお、従前の例による。
(2) この通達の実施の際、現に作成され、備え付けられ、又は保存されている記録、簿冊及び帳簿等は、この通達により作成され、備え付けられ、又は保存されている記録、簿冊及び帳簿等とみなす。
(3) この通達の実施後に法附則第3条の規定による改正前の民事訴訟法(明治23年法律第29号)の規定による不動産の取調べを命ぜられた場合には、現況調査等事件簿に登載するものとし、登載箇所の「備考」に「取調べ」と記載する。この場合、当該事件簿を現況調査事件及び不動産取調事件の別に区分し、又は別冊とすることができる。
(4) この通達の実施前に完了していない執行官の現況調査に係る手数料の加算の基準については、なお従前の例による。
付 記(平10.11.19民三第575号)
この通達は、平成10年12月16日から実施する。
付 記(平11.6.15民三第266号)
1 この通達は、平成11年7月1日から実施する。
2 この通達の実施前に完了していない執行官の現況調査に係る手数料の加算の基準については、なお従前の例による。
付 記(平14.2.15民三第42号)
この通達は、平成14年4月1日から実施する。
付 記(平15.3.26民三第143号)
この通達は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日(平成15年4月1日)から実施する。
付 記(平16.2.6民三第46号)
1 実施
この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年法律第108号)及び担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)の施行の日(平成16年4月1日)から実施する。
2 経過措置
この通達の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これを使用して差し支えない。
付 記(平16.12.1民三第000111号)
1 この通達は、破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から実施する。
2 この通達の実施前にされた破産の申立て又はこの通達の実施前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件における財産価額評定の立会い事件についての記録及び帳簿の作成及び保管については、なお従前の例による。
付 記(平17.12.12民三第001005号)
この通達は、平成18年1月1日から実施する。
付 記(平18.2.8民三第000031号)
この通達は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から実施する。
付 記(平20.11.18民三第000906号)
この通達は、平成21年12月1日から実施する。
付 記(平20.12.11民三第000960号)
この通達は、平成21年1月5日から実施する。
付 記(平26.3.20民三第276号)
この通達は、平成26年4月1日から実施する。
付 記(令2.1.21民三第681号)
1 実施
この通達は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)の施行の日(令和2年4月1日)から実施する。
2 経過措置
この通達の実施前に完了していない執行官の現況調査に係る手数料の加算の基準については、なお従前の例による。
付 記(令2.9.4民三第388号)
この通達は、特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)附則第1条第3項に掲げる規定の施行の日(令和2年10月1日)から実施する。
付 記(令3.6.28民三第195号)
1 実施
この通達は、令和3年7月1日から実施する。
2 経過措置
この通達の実施の際、従前の別紙様式第8による帳簿の用紙が残存している場合には、これを使用して差し支えない。
付 記(令3.11.26民三第303号)
この通達は、令和4年1月1日から実施する。
付 記(令4.7.28民三第257号)
1 実施
この通達は、令和4年8月1日から実施する。
2 経過措置
この通達の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これを使用して差し支えない。
付 記(令5.2.10民三第18号)
この通達は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年2月20日)から実施する。
付 記(令5.6.27民三第216号)
1 実施
この通達は、令和5年7月3日から実施する。
2 経過措置
この通達の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、これを使用して差し支えない。
( 別表第1 )
| 事件種別 | 記録符号 |
| 1 金銭債権についての動産に対する強制執行(罰金、科料等の徴収を含む。) 2 動産を目的とする担保権の実行としての競売(その例による場合を含む。) |
執イ |
| 3 法第168条第1項又は第169条第1項の規定による引渡し又は明渡しの強制執行 4 法第171条第1項の規定による決定に基づく執行 5 法の規定に基づく執行官以外の者の求めによる援助 6 売却のための保全処分等、買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等、最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等又は担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の執行 7 船舶国籍証書等又は航空機登録証明書等の取上げ(仮差押えの執行として行われる場合を除く。) 8 民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の引渡命令の執行 9 差押物の引渡命令の執行 10 不動産強制管理又は担保不動産収益執行における管理人の事務 11 法第116条第1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の保管人の事務 12 法第175条第1項又は第2項(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第140条第1項において準用する場合を含む。)の規定による子の監護を解くために必要な行為 13 その他法令の規定により民事執行の手続において執行官が取り扱うべきものとされている事務(現況調査、売却の実施、内覧及び「執イ」又は「執ハ」の記録符号が付される事務を除く。) |
執ロ |
| 14 仮差押えの執行 15 仮処分の執行 16 その他特別法に基づく保全処分の執行 |
執ハ |